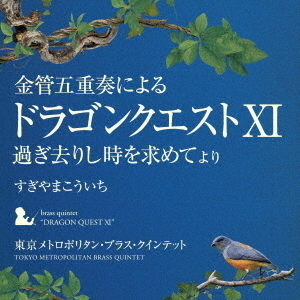 |
金管五重奏による「ドラゴンクエストXI」過ぎ去りし時を求めて より すぎやまこういちスペシャル・アレンジ企画で大好評の、金管五重奏による『ドラゴンクエスト』シリーズ。『「ドラゴンクエストXI」 過ぎ去りし時を求めて』より名曲を、東京都交響楽団の実力派メンバーで構成された“東京メトロポリタン・ブラス・クインテット”の演奏で収録。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
シューベルト:ピアノ三重奏曲第1番&第2番 他2009年クララ・ハスキル国際ピアノ・コンクール優勝者、アダム・ラルーム+2017年エリザベート王妃国際音楽コンクールで優勝したチェリスト、ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール+大阪出身で2000年メニューイン国際コンクール・ジュニア部門優勝のヴァイオリニスト、梁美沙(ヤン・ミサ)の3人によるトリオ・レ・ゼスプリ。彼らは2009年に初めて共にコンサートを行い、互いの音楽性に共感し、2012年正式にピアノ・トリオ<トリオ・レ・ゼスプリ>を結成。パリのシャンゼリゼ劇場でデビュー後、ナントと東京のラ・フォル・ジュルネ音楽祭をはじめ数々の音楽祭に参加し、注目を集めてきました。今回のアルバムでは、実に緊密なアンサンブルと様式感に優れたアプローチによってシューベルトに取り組み、またロマン的情感に溢れた語り口で各曲の魅力を余す所なく引きだしています。残念ながら彼らは解散を発表しており、今作が<トリオ・レ・ゼスプリ>としてのラスト・レコーディングとなります。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
エミール・ハルトマン:室内楽作品集1836年、エミール・ハルトマンはデンマークの作曲家、ヨハン・ペーター・エミリウス・ハルトマンの息子として芸術一家に生まれました。幼少時から作曲を学びましたが、故郷デンマークでは父の影に隠れがちな存在で、留学先のドイツで活躍の場を広げたようです。ハルトマン作品の多くは、楽譜も残っておらず、長い間忘れ去られていましたが、このアルバムでは、デンマークのヴァイオリニスト、エリザベス・ツォイテン・シュナイダーが、ハルトマンが得意とした室内楽に光を当て、ドイツとベルギーから精鋭音楽家を集めて録音、ハルトマンのロマンティックで美しく技巧的な作品を蘇らせました。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
ブラームス:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ全3曲作品の核心に迫る見事なコラボ!注目のヴァイオリニスト、川口堯史デビュー!ピアノは橋本京子。ダイナミックな若さと熟達のピアノとのDUOがぐいぐいと聴き手を引き込む。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
ブラームス、フランク、クララ・シューマン、ロバノフ:作品集2017年と2018年に国際コンクール“Global Music Awards”で金賞を獲得し、またグラミー賞にもノミネートされたヴァイオリニスト、エルミラ・ダルヴァローヴァ。4歳からヴァイオリンを始めた彼女は、メトロポリタン歌劇場管弦楽団で史上初の女性コンサートマスターとなり、カルロス・クライバーなどの大指揮者たちの元で演奏するなど華々しい活躍をしてきました。録音も数多く、NAXOSレーベルへのアルファーノ作品をはじめ、いくつかのレーベルより古典派からピアソラまで様々な作品をリリース、いずれも高い評価を得ています。共演するロバノフはロシア出身の大御所で、かつてはスヴャトスラフ・リヒテルとピアノ・デュオを組んで活動しており、また作曲家としてシュニトケにも認められ、師事しました。これまでに2作のオペラをはじめ、宗教曲、管弦楽曲、室内楽曲の分野で多くの作品を発表しています。このアルバムでは、そんな才能溢れる二人がロマン派を代表する名作を演奏。ロマンティックなクララ・シューマン、落ち着いた風情のブラームス、第1楽章から終楽章まで緊張感漲るフランクと、変幻自在な表現を繰り広げています。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
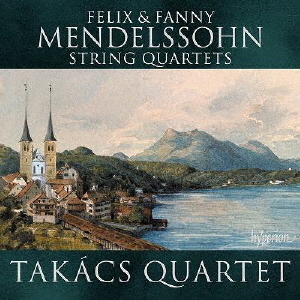 |
フェリックス&ファニー・メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲集¥${PRICE} |
 |
 |
MOMENTUM作曲家、ピアニスト、トロンボーン奏者、マルチな才能を持つマーティン・プタークとトランペット奏者マーティン・エーベルル。2012年から様々な形でコラボレーションを行ってきた二人によるアルバムです。このプロジェクトのきっかけは2018年にウィーンの美術史美術館で行われた展覧会『Ganymed Nature』であり、そこで展示されていたブリューゲルの「暗い日」をイメージしてまず「Twilight Train」が作曲されたのち、観客からの高評価を受けこのアルバムが制作されました。トラック4、5、6、8は2人の共同作品で、1、2、3はプタークの作品、7、9はエーベルルの手による曲です。基本的に落ち着いたピアノの音色が用いられていますが、時にエレクトロニクスやパーカッションなどが音色に彩りを添えています。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
アレックス・バラノフスキの肖像多くの映画音楽と、英国ロイヤル・バレエやオランダ国立バレエとのコラボレーションなどで知られる英国の作曲家、アレックス・バラノフスキの作品を集めたアルバム。演奏はANALEKTAの看板ヴァイオリニストであるアンジェル・デュボーと、彼女が主宰する弦楽アンサンブル「ラ・ピエタ」によるもの。これまでも美しいアルバムを数多くリリースし、ヒットを飛ばしてきた彼女たちならではの1枚で、エンニオ・モリコーネやフィリップ・グラス、マイケル・ナイマンを思わせる抒情的な美しさに溢れています。デュボーらの委嘱作品であり、ポーランド語で「春」を意味する『WIOSNA』は、バラノフスキにとって「これまでで最も個人的な作品」とのことで、彼の祖父がシベリアの強制収容所で1941年に書いた詩(ブックレットに英訳含め掲載)を元にしているとのこと。寒々とした中にも希望のような美しさを湛えた作品です。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
Symmetria Pario:Creation創造的な活動をしているフィンランド生まれの二人の演奏家が書かれたばかりの最新作品に取り組んだアルバム。タイトル通りの「創造の瞬間」が味わえます。アルバム・タイトルは量子物理学の概念から採られ、この世界の創造の瞬間を指しているそうです。収録曲中6曲は世界の創造の瞬間をイメージした作品として委嘱されたものですが、プロデューサーは「科学的な知識を一切抜きにして、想像力を働かせながら聴いてみてください」とのこと。ペッカ・クーシストはシベリウス・コンクール優勝後、世界的に活躍を続けるヴァイオリニストで、最近は指揮にも取り組んでいます。ヨーナス・アホネンはパトリツィア・コパチンスカヤとのデュオ活動でおなじみのピアニスト。ピリオド楽器による古典派音楽から最新の作品まで時代を越えたレパートリーで活躍しています。録音に際しては、かつてフランク・シナトラが所有していたマイクAKG C24と、Yarlungのエグゼクティブ・プロデューサー兼デザイナーのエリオット・ミルウッドが制作した真空管マイク・アンプを用いています。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
偉大な芸術家の想い出に(ハイブリッドCD)人気ピアノ・トリオ「椿三重奏団」のセカンド・アルバムです。デビュー・アルバム「メンデルスゾーン&ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番」では、艶やかで薫り立つようなカンタービレが聴く者の琴線に響き「レコード芸術誌特選盤」に選出されてベストセラーとなりました。このアルバムでは一転、ロシア音楽を代表するチャイコフスキーとショスタコーヴィチの名作による、その重厚でエモーショナルなアンサンブルが圧巻の魅力となっています。眼前で繰り広げられる丁々発止のまさに手に汗握る迫真の演奏が、DSD11.2MHz 超ハイレゾレコーディングにより刻印されました。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
サン=サーンス:チェロ協奏曲 第1番注目のチェロ奏者ブリュノ・フィリップチェロの最強名曲アルバムの登場!驚異的な高解像度新時代のフランクのソナタ決定盤!! (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
ゾルターン・セーケイ ソリストと弦楽四重奏の録音集バルトークのヴァイオリン協奏曲第2番の初演やルーマニア民俗舞曲の編曲で、またハンガリー弦楽四重奏団としての録音で知られるゾルターン・セーケイ(1903-2001)の復刻盤。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
ギャラント様式による古典派時代の室内楽曲ハイドン中期以降の近代型弦楽四重奏曲が普及するより前、ギャラント様式と呼ばれるメロディ中心のわかりやすい音楽様式が流行した1770年代近辺の、フルートと弦楽器のための室内楽曲を集めたアルバム。現代では多くの場合フルートと弦楽三重奏による、いわゆるフルート四重奏の形態で演奏される曲が大半ですが、優れた古楽奏者が多く活躍するベルギーのブリュッセルで結成されたWIGソサエティの演奏家たちはルーティン的な解釈を離れ、チェロ・パートと明記されていないこれらの曲の低音部にコントラバスを使用、さらに(18世紀後半にも現役で使われていた)チェンバロを通奏低音楽器として導入し、驚くほど瑞々しい音響世界を描き出してゆきます。楽器の選択や細部の装飾音などが演奏者に委ねられていた当時の楽譜の読み方として適切でありながら、導き出される音の印象は一般的なフルート四重奏とは全く違う新鮮さ。高音部と離れたコントラバスの音の動きも、チェンバロのみならず各パートが繰り出す機知に富んだ装飾音も絶妙です。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
バワーズ:若き日の自分へ、シェーンベルク:室内交響曲第1番2011年にセロニアス・モンク国際ジャズ・ピアノ賞を受賞し、アカデミー賞の短編ドキュメンタリー部門を受賞したピアニスト・作曲家クリス・バワーズの「For A Younger Self=若き日の自分へ」。コロナ禍のパンデミックの中で書き上げられたこの作品は、映画音楽作曲家として名を上げた彼の初の管弦楽作品であり、若者が自身の問題を克服し、成長していくという物語をヴァイオリン協奏曲の形式で描こうとしています。ヴァイオリン独奏は、グラミー賞受賞バイオリニストのチャールズ・ヤンが担当。併録のシェーンベルクは編成を拡大した、いわゆる「フル・オーケストラ」版と呼ばれるもの。両曲ともカルロス・イスカライが指揮するアメリカン・ユース・シンフォニーが見事にバックを務めています。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
ミヒャエル・ハイドン:6つの弦楽四重奏曲 MH308?313ヨーゼフ・ハイドンの5歳年下の弟ミヒャエル・ハイドンは、モーツァルトと親交があり、作品を共作したこともありました。かつてモーツァルトの交響曲第37番と呼ばれていたものがミヒャエルの作だったように、その作風もよく似ています。兄ヨーゼフやモーツァルト同様にあらゆるジャンルで多数の作品を書いたミヒャエルですが、特に室内楽は作品数も多く、彼の創造性がよく発揮されています。ここに収められた弦楽四重奏曲でも、優雅な旋律、時には荒々しさも感じさせる短調の楽章など聴きどころは多く、まさに兄ヨーゼフとモーツァルトの間に位置するような特徴を感じさせます。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
マヤ・オゾイニク:Doorwaysスロヴェニア生まれのボーカリスト、フルート奏者、作曲家マヤ・オゾイニクのアルバム。自然の音を加工・変調して電子音や楽器と組み合わせた「Doorways #09」、ギリシア神話をテーマにして聴き手を夢幻的な音の世界へいざなう「Blende #01」の2部で構成されています。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
シュテルケル:ピアノ三重奏曲集、四重奏曲ヨハン・フランツ・クサーヴァー・シュテルケルは、ヴュルツブルク生まれのピアニストで作曲家。幼少期、継父によって音楽活動の制約を受けていましたが、母親の支援でピアノを始め、音楽の才能を開花させました。その後、14歳でヴュルツブルク大学に進学し、聖職者を目指して学びながら音楽活動にも注力、1774年には司祭となり、平行して交響曲や宮廷歌手のためのアリアを作曲、評価を高めました。彼の8曲の交響曲は、パリの「コンセール・スピリチュエル」で1777年からの5年間に50回以上も演奏され、1777年から79年の間にパリで最も多く作品が演奏された作曲家となりました。彼は歌劇と十数曲の交響曲に加えて、数多くのピアノ三重奏曲と四重奏曲を作曲。この作品30は1789年にアルタリア社から出版され「心地よい流れ、歌のような旋律、和声の統一が評価されました。とりわけ、鍵盤楽器が主導的役割を担うことが多かったこの時代の作品としてはヴァイオリンとチェロの役割が強調されています。ピアノ四重奏曲は1804年の作品です。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
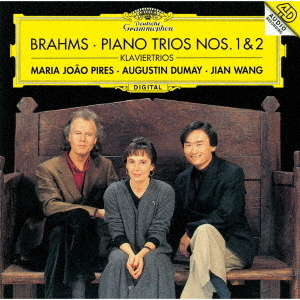 |
ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番&第2番ポルトガル・リスボン出身で2014年に70歳を迎えるピアニスト、マリア・ジョアン・ピリスの来日記念盤。本作は、ピリス&オーギュスタン・デュメイにジャン・ワンを加えたトリオによる録音の第1弾。卓越した個性が一体となり、新鮮で魅力溢れるアンサンブルを聴かせてくれる作品。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
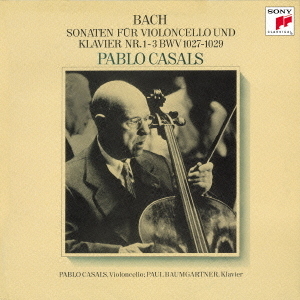 |
J.S.バッハ:チェロ・ソナタ(全3曲)“ソニー・クラシカル名盤コレクション1000”第2弾。バッハ没後200年の1950年、世界的チェリスト、パブロ・カザルスを慕いフランスのプラードに集まった音楽家たちが音楽祭を立ち上げ、当時隠遁生活を送っていたカザルスもこれに応じて演奏活動を再開。本作はその年の音楽界において、パウル・バウムガルトナーのピアノ伴奏で演奏したバッハのチェロ・ソナタを録音したアルバム。バッハを“最良の友”としていたカザルスの、深遠で自由な演奏を収録。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |
 |
ベートーヴェン:弦楽五重奏曲集ケルンWDR放送響のメンバーにより様々なアンサンブルのアルバムをリリースする企画の第一弾。2017年にPentatoneレーベルからリリースしたブラームスが好評を博した弦楽五重奏のメンバー(第2ヴァイオリンのみ入れ替え)による、ベートーヴェンが登場です。まだ若々しさを残す1801年作曲のOp.29と、手法も曲想もたいへん充実した1817年作曲のダイナミックなOp.104、同じ年に書かれごく短い曲の中に複雑な技法を盛り込んだフーガOp.137を収録。経験豊富なメンバーならではの深い譜読みとしなやかで力強いアンサンブルが、作品の魅力を十二分に伝える快演です。 (C)RS ¥${PRICE} |
 |